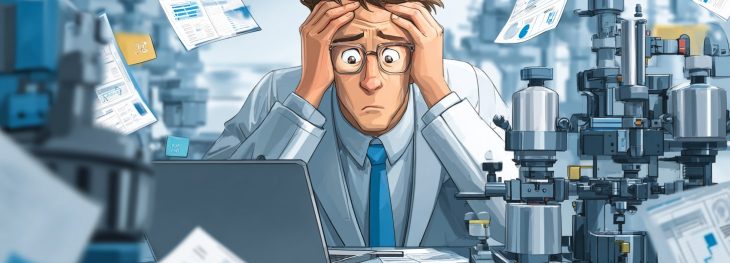「昨日と設定は同じはずなのに、なぜか今日の塗布量は安定しない…」
「隣のラインと同じ装置、同じ設定なのに、ウチだけ不良が多いのはなぜだ?」
生産現場で工業用ディスペンサー装置を使っていると、こんな風に頭を抱えることはありませんか。
こんにちは。
生産技術エンジニアとして15年間、液剤塗布プロセスの改善に携わり、年間100件以上の塗布不良を解決してきた田中です。
その経験から断言できるのは、ディスペンサーの塗布不良の原因は、装置の設定値だけにあるわけではないということです。
むしろ、見落とされがちな「環境」や「機械の細部」にこそ、品質を左右する本当の要因が隠れています。
この記事では、かつての私と同じように悩むあなたのために、同じ機種・同じ設定でも塗布結果がばらつく「落とし穴」の正体と、明日から現場で実践できる具体的な対策を徹底解説します。
この記事を読めば、あなたはもう原因不明の不良に悩まされることはありません。
目次
装置の外に原因が?見落としがちな3つの「環境要因」
多くの場合、私たちは装置のディスプレイに表示される設定値ばかりに気を取られがちです。
しかし、ディスペンサーは非常に繊細な装置。
その性能は、装置を取り巻く「環境」によって大きく左右されます。
要因1:液剤(材料)そのものの状態変化
まず疑うべきは、ディスペンサーに投入する前の「液剤」そのものです。
特に液剤の「粘度」は、吐出量を決める最も重要なパラメータの一つと言えます。
例えば、朝一番の冷えた液剤と、日中の室温に温められた液剤とでは、粘度が全く異なります。
温度が上がれば粘度は下がり(サラサラになり)、吐出量は増える傾向にあります。
逆に温度が下がれば粘度は上がり(ドロドロになり)、吐出量は減ってしまいます。
また、液剤をシリンジやタンクに充填する際に、気泡が混入してしまうことも大きな問題です。
気泡がノズルを通過する瞬間に、塗布が途切れたり、量が極端に少なくなったりする「吐出不良」を引き起こします。
要因2:供給圧力の「見えない」変動
ディスペンサーにエアを供給しているコンプレッサーの圧力は、本当に安定しているでしょうか。
工場全体のエア使用量が増える時間帯に、元圧がわずかに低下しているかもしれません。
たとえディスペンサー手前のレギュレーターで圧力を調整していても、その大元が不安定では意味がありません。
この「見えない圧力変動」が、設定時間を変えていないのに吐出量がばらつく原因になっているケースは、私が経験した中でも非常に多かったです。
要因3:温度・湿度という静かなる敵
液剤の温度だけでなく、工場内の室温や湿度も無視できない要因です。
特に、湿度の影響を受けやすい嫌気性の接着剤などを使用している場合、季節や天候によって硬化速度が変わり、ノズル詰まりの頻度が変わることがあります。
また、夏場のエアコンの風が装置に直接当たっているだけで、ディスペンサー本体や液剤が冷やされ、吐出が不安定になることもありました。
ディスペンサーは、私たちが思う以上にデリケートな装置なのです。
装置内部に潜む!4つの「機械的要因」
環境に問題がないとすれば、次に目を向けるべきは装置の内部です。
毎日使っているからこそ見過ごしてしまう、機械的な要因が隠れているかもしれません。
要因1:ノズル・ニードルの摩耗と詰まり
液剤の出口であるノズル(ニードル)は、いわばディスペンサーのペン先です。
毎日液剤と接触し、圧力がかかるため、先端は少しずつ摩耗していきます。
先端が摩耗して形状が変われば、当然、液剤の出方も変わってしまいます。
また、作業中断時にノズル先端で液剤がわずかに硬化し、それが徐々に蓄積して内部を塞いでしまうこともあります。
見た目は綺麗でも、内部で詰まりかけていることは珍しくありません。
要因2:シリンジ残量とピストンの罠
シリンジタイプのディスペンサーでよくあるのが、液剤の「残量」による吐出量の変化です。
シリンジに液剤が満タンの状態と、残りわずかの状態とでは、ピストンが液剤を押す際の抵抗や応答性が微妙に変わります。
これにより、特に精密な塗布が求められる場合に、吐出量のばらつきとして現れることがあります。
常に同じ残量で交換する、といったルール作りも時には有効です。
要因3:チューブの長さと材質
液剤タンクからバルブまでをチューブで配管している場合、その「長さ」と「材質」が影響することもあります。
チューブが長すぎれば圧力損失が大きくなり、バルブの応答性が悪化します。
また、チューブの材質が使用する液剤に適していないと、チューブが膨潤したり、逆に硬化してしまったりして、安定した供給を妨げる原因となります。
要因4:消耗品の「個体差」という現実
バルブ内部のパッキンやOリングといった消耗品。
これらは定期的に交換が必要ですが、実はメーカーや製造ロットによって、寸法や硬さに微妙な「個体差」が存在します。
前回交換した時は問題なかったのに、今回交換したらなぜか調子が悪い、という場合は、この個体差を疑ってみる必要もあるでしょう。
安定稼働のためには、信頼できるメーカーの純正品を使うことが基本です。
明日からできる!安定稼働を実現する3つの鉄則
では、これらの多様な要因にどう立ち向かえばよいのでしょうか。
私が現場で徹底してきた、シンプルかつ効果的な3つの鉄則をご紹介します。
鉄則1:条件の「見える化」と記録の徹底
まずは、これまで感覚で管理していた項目を、すべて数値で「見える化」し、記録することから始めましょう。
- 液剤温度: 投入前に非接触温度計で測定し記録する
- 供給圧力: 始業時に圧力計の値を読み、記録する
- 室温・湿度: 温湿度計を設置し、定時に記録する
- 消耗品交換日: ノズルやパッキンの交換日と、交換した担当者名を記録する
これらのデータを毎日記録し続けることで、不良が発生した際に「何がいつもと違ったのか」を客観的に分析できるようになります。
鉄則2:始業前点検チェックリストの導入
トラブルの多くは、事前のチェックで防ぐことができます。
以下のような項目を盛り込んだ、誰でも同じように点検できるチェックリストを作成し、毎日の習慣にしましょう。
- 供給圧力は規定値か?
- ノズルに詰まりや摩耗はないか?
- 液剤に気泡の混入はないか?
- 各部から液漏れやエア漏れはないか?
- 試し打ちの吐出量は正常か?
この一手間が、一日の安定稼働を約束し、大きなトラブルを未然に防ぎます。
鉄則3:「なぜなぜ分析」で根本原因を断つ
万が一、不良が発生してしまった場合、「設定を少し調整してごまかす」のは最悪の選択です。
必ず立ち止まり、「なぜこの不良が起きたのか?」を最低5回は繰り返してください。
なぜ吐出量が減ったのか? → ノズルが詰まっていたから
なぜノズルが詰まったのか? → 休憩中に液剤が硬化したから
なぜ休憩中に硬化したのか? → ノズルの洗浄ルールがなかったから
なぜルールがなかったのか? → …
このように掘り下げることで、表面的な現象ではなく、プロセスの問題点という「根本原因」にたどり着くことができます。
これこそが、再発を防止する唯一の方法です。
まとめ:ディスペンサーを「管理」する意識が品質を決める
今回は、同じ設定でも塗布結果がばらつく原因と、その対策について解説しました。
- 見えない要因を疑う: 塗布不良の原因は、設定値だけでなく「環境要因」と「機械的要因」にも潜んでいる。
- 環境要因: 液剤の状態(温度・気泡)、供給圧力、工場の温湿度など、装置の外側にも目を向ける。
- 機械的要因: ノズルの摩耗や詰まり、シリンジ残量、消耗品の個体差など、装置の細部を点検する。
- 安定稼働の3鉄則: 「見える化と記録」「始業前点検」「なぜなぜ分析」を徹底し、トラブルを未然に防ぎ、根本から断つ。
ディスペンサーは、ただスイッチを入れれば同じ結果を出してくれる魔法の箱ではありません。
その日のコンディションを正しく把握し、常に最高のパフォーマンスを発揮できるよう「管理」してあげる意識が不可欠です。
この記事が、あなたの現場の品質安定化に向けた第一歩となれば、これほど嬉しいことはありません。